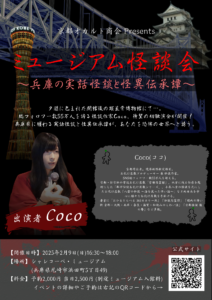境港妖怪検定対策・栃木県の妖怪5選
境港妖怪検定・中級の公式テキストブック「決定版 日本妖怪大全 妖怪・あの世・神様/水木しげる著」(以下「日本妖怪大全」という)の”妖怪”カテゴリに記載されている栃木県の妖怪をすべてまとめました。
・直接的な地名が書かれていないものは省略しています。
・旧地名は現在の都道府県に振り分けており、複数の都道府県にまたがる場合は、そのすべての都道府県に振り分けています。
・一般的に出現地が判明している妖怪でも、日本妖怪大全に出現地が記載されていない場合は含めていません。
関東のオサキ
基本情報(日本妖怪大全での記載内容)
栃木県、または埼玉県や茨城県などでいう憑き物の一種。
「オサキが憑く」ともいい、オサキに憑かれた人は大食いをするようになったり、前歯で物を噛むようになる。
オサキは常に群れで行動すると言われており、その見た目はハツカネズミよりも少し大きく、鼬のような姿をしており、色は茶色、橙色、灰色、または茶色と灰色の二色などと様々で、頭からしっぽまで黒い一本線の模様があるとも言われている。
昭和初期ごろまで「オサキが憑く」ということはよくよくあったようで、水木しげる先生の「日本妖怪大全」では栃木県ではないが、女性がオサキに憑かれた話が紹介されている。
それは、こんな話である。
昭和21年夏、群馬県邑楽郡で一人の女性が突然精神に異常をきたした。
なんの前触れもなく、興奮した様子で「オーサキが来た、オーサキが来た」と叫び、暴れ始めたのである。
家族も彼女の突然の変貌に怯えながらも、必死に何とかしようと試みたがどうすることもできず、彼女は自宅で監禁されることになった。
1ヶ月、2ヶ月と監禁が続くが、それでも精神状態は一向に良くならず、半年経ってからようやく正気に戻ったという。
実は、彼女の家の近所にオサキを飼っているという家があり、そこの人にオサキを憑けられたのではないかという噂である。
オサキを飼っている家のことを「オサキ屋」と呼んでいる。
追加情報
江戸時代中期ごろから、文献上に現れはじめ、漢字では「お先」「尾裂き」「尾先」とも表記される。
また地方によっては「オーサキ」「オサキ狐」「オーサキドウカ」とも呼ばれている。
「尾先」という表記は、九尾の狐が討たれた際に尾の先から、このオサキが生まれたからだと言われている。
また別表記の「尾裂き」はその字面の通り、尾っぽが裂かれているからともいう。
見た目に関しては、主に狐、また鼠やオコジョのような小動物のような姿として表現されるが、珍しいものでは梟と鼠の雑種というものもある。
修験者が竹筒に入れて使役する管狐や、東北に伝承が残る飯綱という憑き物と特徴が非常に似通っており同一視されることもある。
オサキは個人にも憑くが、家筋にも憑く場合があり、その場合は憑いた一族は裕福になると言われている。
しかし、反対に近隣の家は不幸になると言われている。
それはオサキ持ちの家が、よその家の物を欲しがるとオサキがそれを奪ってきたり、奪えないものの場合は壊したりするからであり、オサキ持ちが他人を憎むとその人を病気にしたり、精神を錯乱させて最後には殺してしまうと言われている。
そのため、オサキ持ちは差別や迫害の対象となっていることが多く、婚姻が破談になることもあったという。
オサキに憑かれた人は極端に大食いになるが、身体はどんどん痩せ細っていき、次第に命を落としてしまう。
その他にも発熱、精神異常、奇行に走るなどの症状がある。
個人に憑いたオサキは祈祷で祓うことができるが、家に憑いたオサキは祓うことはできないと言われている。
しかし、地域や文献によってはオサキを抱えたまま川に入ると離れると書かれているものもある。
ご飯のお椀やお櫃を叩くとオサキが寄ってくる、墓地の苔をオサキに近付けると嫌がるという俗信も伝承されている。
関東地方や中部地方のとオサキは広く分布しているが、実は江戸にオサキはいないらしく、その理由としてオサキが戸田川(荒川)を渡れなかったとも、関東八州の狐の親分の王子稲荷が防いでいるとも、九尾の狐が化けた殺生石の破片(もしくは尻尾)がオサキの元なので、その破片が江戸に落ちなかったから、とも言われている。
関連妖怪として、山オサキや里オサキというものが群馬県で伝承されている。
九尾の狐
基本情報(日本妖怪大全での記載内容)
この世が泥海のように混沌としていた時代、悪い陰気が凝り固まって生まれたのがこの妖狐。
そして、途方に暮れるほど長い年月を経て、九つの尻尾を持ち、黄金の体毛に覆われ、白い顔を持つ、白面金毛九尾の狐となった。
九尾の狐はこれまでに数々の国の政治を惑わせて、滅ぼしてきた大妖怪だとされる。
中国の殷やインド、そして日本にも。
日本には遣唐使の吉備真備の船に少女の姿に化けて乗り込んできたと言われる。
美女に化けた九尾の狐は玉藻前と名乗って、宮廷に潜り込み天皇から寵愛を受けたという。
しかし、陰陽師の安倍泰成に正体を見破られ、那須にまで逃げていった。
そして、那須の地で軍勢に囲まれて討ち取られてしまったという。
九尾の狐の死体は殺生石に変化し、今でも那須の地に残っている。
殺生石は硫化水素や炭酸ガスなどを発生させ、人や動物に被害を及ぼしているという。
追加情報
平安時代末期に鳥羽上皇に寵愛されていた。
殺生石は会津(現在の福島県喜多方市)の示現寺の玄翁和尚に打ち壊され、日本各地に欠片が飛び散る。
その欠片が各地の憑き物(オサキ狐、トウビョウ、犬神、牛蒡種など)になったとも言われている。
また、福島県の摺上原の人取石や大分県の九重町の殺生石は、那須の殺生石の欠片と伝わる。